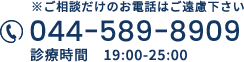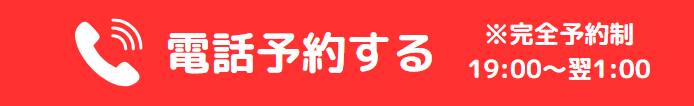2025.10.03犬の痙攣(けいれん)が止まらない!気になる原因や症状を徹底解説

愛犬の体が突然硬直し、ぴくぴくと筋肉が小刻みに震えている様子を初めて見ると「もしかして痙攣?」と驚き慌てますよね。
これまでに犬の痙攣を見たことがない飼い主様にとって、突然の愛犬の異変への心配は相当なものでしょう。
犬の意思にかかわらず筋肉が勝手に動き、意識を失うケースもあります。犬の痙攣は、実は緊急性が高く、早急な対処が必要というケースもあります。
いざというときに落ち着いて行動できるように、犬の痙攣の原因や症状まで詳しく知っておくことが大切です。
犬の痙攣(けいれん)とはどんな症状なの?

次に、犬の痙攣についてどんな症状かご紹介していきます。
犬の筋肉が異常を起こす状態を「痙攣」と言う
犬の痙攣は、身体の硬直や大きな震えのような発作が起こります。一般的には、犬自身の意識とは無関係に勝手に体が硬直して動くことが多いです。
犬の意識とは関係なく、
・筋肉が硬直してピーンと足が伸びている
・バタバタと足を動かしている
・ぴくぴくと震えている
・激しく動きまわる
・くるくると回っている
など筋肉が動くことを痙攣と言います。
“震え”とは違う
痙攣でも“震え”のような症状は起こりますが、一般的な犬の「震え」と「痙攣」は意味合いが異なります。
痙攣の場合、犬は自身のコントロールができない状態です。意識を失ったりすることもあります。
一方、一般的な震えの場合、
・寒い
・緊張している
・ストレスが大きい
・興奮している
といった、特定の何らかの理由から体をぶるぶる震わせるケースが多いです。
たとえば、「病院に行こうとすると震える」「知らない人が来ると震える」といった感じで、痙攣とは違って意識もはっきり時間的にも長めでしょう。
ただ、「震え」に関しては、痙攣でも見られる症状です。意識が朦朧としている震えや、急に何の前触れもなく起こる震えなどは何らかの病気が背景にあるケースも。様子を見ながら動物病院に相談することも大事です。
犬の痙攣(けいれん)を引き起こす代表的な病気とその特徴を詳しく解説
犬の痙攣を引き起こす代表的な病気について見ていきましょう。
原因①:てんかん
脳が興奮して神経に異常をきたし、さまざまな症状を起こすのが「てんかん」という脳の病気です。そわそわする、うろうろするといった発作の前兆が見られる場合もあります。
てんかんになると、
・痙攣
・よだれが垂れる
・失禁する
・倒れるくらいヨロヨロ歩く
などいろいろな症状が起こります。
てんかんには、
・脳の異常はないのに起こる原因不明の「特発性てんかん」
・脳の出血や水頭症、脳炎など脳の病気で起こる「構造性てんかん」
などの種類があります。
また、症状の現れ方も
・意識がなくなって全身症状が起こる「全般性てんかん発作」
・体のどこか一部だけに 症候が起こる「焦点性てんかん発作」
などさまざまです。
原因②:中毒
誤食・誤飲がきっかけで中毒を起こし、痙攣の症状が見られることがあります。特に、犬にとって毒性の強い物が体内に入ってしまった場合、リスクが高いです。
ネギ類、チョコレート、殺虫剤、人間の薬など、犬にとって害のある物の誤食は大変危険です。
原因③:脳疾患
脳腫瘍や脳梗塞、脳炎などの脳疾患が痙攣を引き起こすことがあります。特に、高齢の犬は脳腫瘍や脳梗塞を発症しやすいので注意が必要です。
脳腫瘍や脳梗塞になると痙攣のほか、
・視力が低下して物が見えづらそう
・歩きづらそう
・震える
・くるくると回る
・攻撃的な性格になる
・首を傾けることが多い
といった症状も見られることがあります。
痙攣を頻繁に繰り返す場合は、脳の病気を疑い動物病院の受診をおすすめします。
原因④:筋肉の疲労
小刻みな震えのような痙攣の場合、
・筋肉を使い過ぎての疲れている
・筋力低下(加齢にともない)
によって起こっている可能性もあります。
特に、年齢を重ねて筋肉が落ちている老犬は筋肉も疲労しやすいです。横になっている際に“ビクッ”と足を動かすこともあります。ただ、これは痙攣ではなく、すぐにおさまるものであまり心配ないことがほとんどです。
原因⑤:低血糖
エネルギーの源とも言えるブドウ糖が血中から急速に不足し、基準値を下回った“低血糖”も痙攣の原因のひとつです。
血糖値が低下することで、元気がなくふらつくようになりますが、症状が進むと「震え」「失禁」「嘔吐」「下痢」「痙攣」を起こすこともあります。
低血糖は、特に身体の小さな犬に起こりやすいと言われています。
原因⑥:腎不全
腎臓病も痙攣を引き起こすことがあります。
腎臓病が進行すると老廃物の排出が難しく「尿毒症」が進行しやすいです。毒素が体内に溜まることで消化器系に異変が起こるほか、痙攣など神経系の症状も起こしやすくなります。
犬の腎臓病は、
・腎機能が急速に低下していく「急性腎臓病」
・少しずつ腎臓にダメージが加わって起きる「慢性腎臓病」
と2つのパターンがあります。
どちらの場合でも、末期症状として見られるのが尿毒症です。
原因⑦:熱中症
犬は、
・気温の高い日に散歩する
・エアコンなしで留守番する
など熱中症を発症しやすい動物です。
熱中症は「身体が熱くなる」「呼吸が荒い」といったものから、重度になると痙攣や意識障害を起こすケースもあります。
愛犬の痙攣(けいれん)が発生した際の飼い主が取るべき適切な対処方法
次に愛犬が痙攣を起こした際に、飼い主さんが気をつけるべきポイントについてご説明します。
冷静に様子を見ましょう
いつもと違う愛犬の様子を見て慌てない飼い主さんはいません。びっくりして当然ですが、まずは落ち着きましょう。
「痙攣かも…!」と思っても、無理に犬の体を触るのは危険です。
たとえ飼い主さんの手でも、痙攣中にはそれを理解できず、触れられると驚き焦ります。
訳が分からず「噛む」「暴れる」といった行動の引き金となる可能性もあるため注意が必要です。
びっくりして押さえつけようとしたら噛まれるケースもあるため、飼い主さんのケガ・犬のケガにもつながります。大きな声を出して犬をびっくりさせるのもやめましょう。
愛犬の安全を確保する
痙攣の症状として、くるくる回るなど激しい動きをする場合があります。ケガをすると大変ですから、クッションや布団などを周囲に置いてぶつからないようにすることが大事です。
くれぐれも「危ないよ!」などと大きな声で犬をびっくりさせないようにしましょう。
発作が何分続くかチェックする
痙攣が起こった場合、「どのくらいの時間続くか」も確認しておきましょう。発作はだいたい3分以内にはおさまることが多く、5分以上も痙攣が続き苦しそうな呼吸をしていると危険と言われています。
1回の発作が5分以上続く状況は「重積発作」と言われ、早めに対処すべきです。
発作が長引く、何度も繰り返す場合は、様子を見てもおさまらないばかりか、脳への損傷がひどく命の危機が起こっている可能性もあります。早急に動物病院で処置してもらうことが必要です。
痙攣の様子を観察する・動画を撮影しておく
愛犬に初めて痙攣が起こると「痙攣なのか?震えなのか?」が判断できずに不安な飼主さんも多いかと思います。突然のことで慌てるかもしれませんが、まずは痙攣の様子を確認しましょう。
動物病院受診の可能性を考え、スマホで動画撮影しておくことをおすすめします。
痙攣が起こると飼い主さんは慌てるため、動物病院を受診したときに「身体のどこが痙攣していたか」が曖昧になることが多いです。動画で痙攣の様子が分かれば、獣医師の正しい診断に役立ちます。
また、痙攣以外に異変が起こっていないかもチェックしておきましょう。
動物病院へ向かう

「痙攣がおさまらない」「何度も繰り返す」危険性が高い痙攣なら、できるだけ早めに動物病院に向かいましょう。
動物病院に連れていく際は事前に電話連絡のうえ、愛犬を安全に守りながら連れていきましょう。
犬の痙攣(けいれん)が止まらない…動物病院で受診する判断基準は?
もう少し様子を見るべきか、それとも動物病院に連絡するべきか、愛犬の痙攣が止まらないと不安ですよね。動物病院で受診した方がいい判断基準についてご紹介します。
5分以上も長く痙攣が続いている
犬の痙攣は2~3分でおさまるケースが多いです。
5分以上も長い時間、痙攣が起こっているなら、すぐにでも動物病院を受診すべきです。痙攣は続く時間が長いほど脳へのダメージが大きくなります。
「もう少し様子を見ようか…」といった自己判断は危険です。
特に、夜の時間帯に起こる痙攣は「病院が閉まっているから」と躊躇しやすいですが、夜間病院にすぐにでも受診したいところです。
痙攣前に誤食・誤飲をしていた
痙攣の原因が“誤食・誤飲”の可能性がある場合、痙攣がおさまっても動物病院に連れていくことが大事です。
痙攣が一過性でも、下痢や嘔吐などそのほかの症状が強まる可能性も考えられます。特に、犬にとって有害な物質を飲み込んだ場合は、中毒症状が強まるケースもあるため注意しましょう。
痙攣後の犬の様子がおかしい
痙攣後にぐったりとしている、嘔吐が強まった、下痢が起こっているなど、犬の体の異変が強まっている場合は動物病院に相談することが大事です。
数分おき、数時間おき…と1日のうち痙攣を繰り返している
1日のうち、何度も痙攣を繰り返しているときは重大な病気が潜み進行している可能性があります。早急に動物病院を受診しましょう。
愛犬の健康と安全を守るために普段から飼い主ができる予防とケアとは

犬の痙攣は、多くの場合、突発的に起こります。飼い主様が予期しないタイミングで痙攣が発生するので、完全なる予防は難しいです。
ただ、痙攣の原因が病気の場合なら、早期発見・早期治療により痙攣を未然に防げる可能性もあります。
ふだんから犬の様子をチェックすることで異変に早めに気づけます。
特に、ふだんから「ふらついて歩く」といった行動が見られる場合は、痙攣のリスクも考えて早めの受診をするようにしましょう。
また、誤食・誤飲の中毒で痙攣を引き起こすケースもあります。人間の食べ物のなかには犬の体に中毒症状を起こすものがあるため、「飼い主さんが有害物質について知識を深めること」と「危険なものを犬の身近に置かないこと」で中毒による痙攣予防は可能です。
まとめ
“痙攣”という言葉は知っていても、実際に愛犬の痙攣を目の当たりにするケースは頻繁にはありません。そのため、初めて痙攣をした様子を見ると慌てる飼い主さんは多いです。
痙攣の症状の原因はたくさんあり、一過性のものなのか、痙攣を起こすほど病状が深刻なのか、その見極めは飼い主さんご自身では難しいでしょう。
夜間に痙攣が起こった場合、「夜間だから・・・」と様子を見られる飼い主さんも多くみられますが痙攣は緊急性が高く命に関わる症状になります。痙攣が起きたらまずは冷静になり、様子を観察・記録した上で早めに受診を強くお勧めします。
当院は、東京・横浜・川崎・千葉の京浜エリアで深夜のペット診療(夜間動物病院)を行っています。犬の突然の痙攣にご不安で受診をご希望の場合は、お電話でご予約のうえ、ご来院ください。