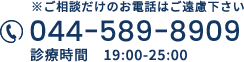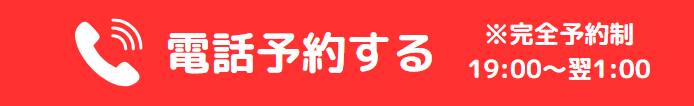2025.10.03犬や猫の嘔吐に血が混じるのはなぜ?吐血の原因や飼い主がまず確認すべきポイントとは

愛犬や愛猫が嘔吐したとき、血が混じるとびっくりしますよね。血を吐くのは普通ではないことですから、少しの量でも飼い主様は不安なはずです。
血を吐くのには何らかの理由があり、体の“どこで出血したか”によって潜んでいる病気も異なります。早急に病院に連れていくべきケースもあります。
今回は、犬や猫が血を吐く原因や吐血を防ぐためにできること、緊急性のある症状など口からの出血について詳しく解説していきます。
犬や猫が血を吐く主な原因や考えられる病気や疾患
犬や猫の嘔吐に血が混じる場合、さまざまな病気や疾患が背景にあります。よくある“吐血”の原因をご紹介します。
口腔内の病気によるもの
犬や猫は歯周病などお口のトラブルはよくあり、進行した際の主な症状が歯肉からの出血です。
歯周病になっている犬や猫は、
・よだれが多くなる
・カリカリのドライフードを嫌がる
・口臭が強い
・食欲不振で体重が減る
など、出血以外にもさまざまな症状を見せます。
また、子犬や子猫の場合、おもちゃや家具、クッションなどさまざまな物に興味を抱く時期。食べ物以外の硬いものを“噛む”ことが日常的ではないでしょうか。家具などの硬いものをガリガリと噛み口腔内が傷つくことも多く、出血しやすい傾向です。
そのほか、歯茎や口のなかに腫瘍や口内炎ができ、腫れによって出血することもあります。
胃腸炎や胃潰瘍などの病気
胃腸炎や胃潰瘍など、消化器官の炎症により吐血することがあります。
犬や猫の胃腸炎は、
・誤飲
・ストレス
・細菌感染
・食べすぎの消化不良
・アレルギー
など多岐にわたる原因から起こる病気です。
胃腸炎で主にみられる症状は嘔吐や下痢といった消化器の症状で、嘔吐物に血が混じることもあります。胃腸内で炎症が起こっているため、犬や猫はお腹に痛みを感じている可能性が高いです。お腹を気にする様子が見られる場合もあります。
異物の誤食によるもの
犬や猫が鋭利な異物を飲み込み、それが食道や消化器官を傷つけて吐血するケースもあります。
人間と暮らしている犬や猫は、さまざまなものを誤食・誤飲する可能性が高いです。
竹串や画鋲、プラスチックの破片、人間の薬の殻などを飲み込んでしまった際、それが体内の粘膜にひっかかり傷つけて出血することもあります。
中毒症状によるもの
犬や猫にとって有害なものを食べて中毒が起こり、それが嘔吐とともに血が混じるケースもあります。
チョコレート、ネギ類、キシリトール、植物、タバコ、乾燥剤、殺虫剤などペット達に害のあるものが多くのご家庭に潜んでいます。中毒を起こした場合、嘔吐や下痢、痙攣、食欲不振といったさまざまな症状が起こります。
誤食した物質の内容にもよりますが、重症になると血が混じる嘔吐が見られることがあります。
鼻炎が重症化
鼻炎が進行して重度になると、“鼻血”の逆流により口から排出されるケースがあります。
犬・猫が口から出血は。「吐血」と「喀血」…どう違う?
口から血を出した場合は、大きく分けて“吐血”と“喀血”という2つのパターンがあります。
吐血
消化器官で起こった出血が嘔吐とともに排出されるのが「吐血」です。
胃や肝臓疾患など、さまざまな原因が考えられます。
喀血
肺や気管支などの呼吸器官で起こった出血が「喀血」です。薄ピンクや鮮血色の液体を咳と一緒に吐くことがあります。
誤食や事故などが原因の可能性も考えられます。
また、気管支や心臓などの疾患が原因で喀血している可能性もあります。
食事・フードが原因で起こる犬や猫の吐血を防ぐ食生活の基礎知識

食事が原因となって吐血が起こることもあります。犬や猫の食事関連における吐血予防の基礎知識について見ていきましょう。
硬い食べ物やおやつなどで吐血することがある
硬い食べ物は吐血の原因となるケースがあります。食べ方によっては口内を傷つける可能性もあるからです。
硬いものを食べる際は、口内を傷つけるような危ない食べ方をしないよう飼い主様が見守ることで危険を回避できるでしょう。
また、体内に入れるものですから、原材料などにも着目し、安心して食べられるものを選ぶことも大切です。賞味期限が過ぎたものなど劣化した食品を与えると胃腸炎のリスクが高まるため注意しましょう。
腐ったフードを与えないように管理する
吐血の原因のひとつに胃腸炎があります。
犬や猫の場合、「腐敗したフード」によってお腹を壊すことがあるため注意が必要です。特に、夏場は室温が暑くなると食べ物の傷みが進みます。食べ残しを数時間も放置し、それを食べて胃腸炎を引き起こすケースがあります。
食べ残しは廃棄し、その都度新鮮なものを与えましょう。
人間の食べ物をむやみに食べさせない
人が食べる食品には、犬にとって有害で中毒を起こす原因となるものも多いです。たとえ少量でも、身体の小さい犬や猫にとってはダメージが大きいケースもあるため注意しましょう。
【緊急疾患】こんな症状があったらすぐ動物病院で診察を受けるべき

そもそも「口から血が出ること」自体が普通ではないことで、犬や猫の体内で健康を害する何かが起こっています。吐血以外に症状が落ち着いていれば、緊急性はないかもしれません。ただ、なかには“すぐにでも”受診すべきケースもあります。
ペットを飼っていれば、吐血・喀血する可能性はあるため、「緊急性が高い出血」を知っておくことが大事です。
できるだけ早急に動物病院に連れていくべき症状は、
・1日のうち、嘔吐を複数回繰り返している
・意識がない、意識朦朧としている
・ぐったりして動かない
・出血量がかなり多い
・激しい咳込み
・呼吸が荒く苦しそう
・毎日必ず吐く
・よだれの量がすごい
・お腹を痛そうにしている
・食べ物を食べなくなった
などです。
動物病院に連れていくタイミングは飼い主様も迷うかもしれませんが、気になったときは動物病院に連絡し相談してみるといいでしょう。
飼い主が自宅でできる犬や猫の吐血時の応急処置と適切な対応方法
犬や猫が血を吐いたとき、応急処置をすぐにできるのは飼い主様だけです。もしものときに慌てず対応できように、飼い主ができる応急処置やチェックするべきポイントをご紹介していきます。
犬や猫を安静にさせる

犬や猫の嘔吐が終わったら、まずは落ち着かせましょう。嘔吐している最中に無理に口中に手を入れると、興奮したり苦しんだりする可能性もあるため避けましょう。
ハーネス・首輪をつけている場合、体を圧迫して苦しみが増す可能性も高いため、取り外すと楽になります。
嘔吐の後は、犬や猫が興奮しないようにケージに入れて安静にさせるのもいいでしょう。
また、動物病院に連れていくために抱っこする際は、呼吸が圧迫されない体勢にしましょう。上を向かせると嘔吐が難しくなり、逆に飲み込んでしまうため注意が必要です。
直前の行動を思い出す
血を吐く前、犬や猫はどんな行動をしていましたか?
遊んでいる最中に急に血を吐いた、テーブルの上のものを物色した後に吐血したなどは異物を誤飲した可能性も考えられます。何かしらを飲み込んだ形跡がないかもチェックしましょう。
また、鼻血や咳込みなどもあったか書き留めておきましょう。
動物病院で問診をする際にスムーズに伝えやすくなります。
出血の量・状態をチェックする
前述したように、吐血と喀血は出血が起こる場所や血の色・状態が異なる場合があります。血の色を観察しておくことで、「どこから出血したか」の判断材料になるため、確認しておきましょう。言葉ではうまく伝えられないことも多いので、写真や動画で撮影しておくのもおすすめです。
吐血した後の犬・猫の体の状態をチェックする
血を吐いた後の愛犬・愛猫の様子を観察しましょう。
血が混じる嘔吐の後、
・咳が止まらない・呼吸が苦しそう
・ぐったりしている
・チアノーゼ(舌の色が青白い)
といった場合は緊急度が高い可能性があります。
絶食と絶水を
嘔吐に血が混じる原因が消化器によるものの場合、食事によってさらに負担をかける可能性が高いです。
犬の様子によっても異なりますが、12~24時間は絶食するのが理想です。
何度も嘔吐している犬・猫に無理やり水を飲ませると逆に負担が大きくなるため注意しましょう。
動物病院で診断が大切
犬や猫の嘔吐に血が混じるのは、病気が進行しているケースが多いです。
「意識がなくぐったりしている」「大量出血している」など、明らかに異常が深刻そうなら迷わずに動物病院に連れていくタイミングになります。
ただ、
・1回だけ吐血したが今は落ち着いている
・ちょっと血が混じっただけ
というケースは、様子見をしてしまいがちかもしれません。
でも、実は何かしらの病気のサインの可能性もあるため、ご不安なときは動物病院での診断が重要です。
また、犬や猫は苦しさを極限まで我慢してしまう習性があり、飼い主様が「大丈夫そう」に思えても実は痛みを抱えているケースもあります。少しでも早く原因を取り除き、適切に対処するには獣医師による診断が大切です。
まとめ
犬や猫は、人間と違って「嘔吐」は珍しいことではありません。ただ、嘔吐に血が混じることは何かしらの病気が潜んでいる可能性が高く、軽視できないことも多いです。
嘔吐したものに赤い血や黒い塊があるとパニックになる飼い主様もいらっしゃるでしょう。
驚くのは当然のことですが、まずは冷静に血の色や量、愛犬・愛猫の様子をチェックしてください。
犬や猫自身も体の異変・不調で苦しんでいるかもしれません。体を圧迫すると負担になるため、安静に落ち着かせましょう。
翌日まで待つことで、症状が悪化する可能性もあります。
当院は、東京・横浜・川崎・千葉の京浜エリアで深夜のペット診療(夜間動物病院)を行っています。愛犬や愛猫が夜間に突然の異変が起こった際、受診をご希望の場合は、お電話にてご予約のうえご来院ください。