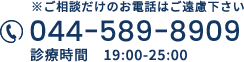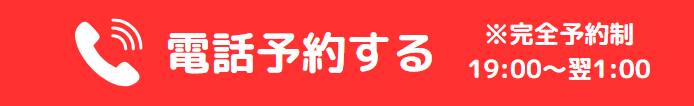2025.10.03愛犬がぐったりしている…考えられる原因や病気、今すぐ受診すべき緊急度の高い症状とは?

いつも元気なはずの愛犬が突然ぐったりして動かないと、「病気ではないか…」「病院にすぐに連れていった方がいいのか…」など心配になりますよね。
犬の元気がなくなる原因はさまざまで、病気が潜んでいる場合もあれば、一時的体調不良で程なくして回復することもあります。
しかし、急にぐったりした、あるいは他の症状も同時に見られる場合は、緊急度の高いサインであることも。
今回は、犬がぐったりする理由に迫るとともに、飼い主様が知っておきたいポイントを詳しくお伝えしていきます。
犬がぐったりしているときに確認すべき症状と初期対応のポイントとは
犬がぐったりしたときに確認すべき症状や対処法などをお伝えします。
犬がぐったりしたら何をすべき?
愛犬がぐったりしていたら、まずは落ち着きましょう。
無理に動かさず、「犬の意識の有無」「呼吸の状態」など愛犬の状態を確認することが大切です。
呼びかけにも反応しない、震えがおさまらないなど、明らかな異常があれば緊急度が高い可能性があります。
また、誤食や誤飲、ケガによってぐったりしていることもあるため、足や口の異常も調べましょう。嘔吐や下痢をしていないか、ぐったりする前の行動も思い出して記録しておくと、動物病院の受診の際に役立ちます。
脱水や熱中症が原因でぐったりしている場合は、水分補給によって体調が回復することもあります。
ただし、注意したいのは「意識の有無」です。意識障害を起こしているときは、誤嚥によって肺炎を起こすリスクがあります。
犬の意識がはっきりし、「自力で立ち上れる・自力で飲める」なら少量の水を与えてもいいでしょう。
しかし、
・反応が薄い、意識朦朧としている
・震えている
・けいれんを起こしている
などの場合は、無理に飲ませずにすぐにでも動物病院に連れていくことが重要です。
年齢によっては重篤度が高い

免疫の低い子犬や高齢犬は症状が急変することも多いです。特に、子犬は低血糖などが原因でぐったりしている場合もあり、放置すると命に関わるリスクもあります。
本来、子犬は元気に動きまわるものですから、ぐったりしているなら何らかの病気の可能性が疑われます。
一方シニア期の犬は、何らかの慢性的な疾患を抱えていることも多いです。それが原因で元気がないこともよくあります。
しかし、高齢犬はそもそも寝ている時間も長くなることから、「元気がないのは年齢のせい」「食事はしているから大丈夫だろう」など、普段との変化を軽視しがちなので注意が必要です。
慢性的な疾患が潜んでいるケースもあるため、元気がないだけでなく、鼻水、咳、下痢・嘔吐などの異変があれば早急な受診が大切となってきます。
また、若く健康な犬でも中毒や熱中症でぐったりすることもありますので油断は禁物です。
犬がぐったりする主な原因と考えられる病気や疾患について解説
ぐったりした症状が見られたとき、まず疑うべきは身体的な原因です。次に具体的な病気や疾患などをご紹介していきます。
感染症やウイルス
感染症やウイルスなどにかかると、体力が奪われてぐったりすることがあります。
特に注意したいのは、以下の病気です。
【犬パルボウイルス感染症】
激しい下痢とともに、嘔吐や脱水なども起こって衰弱します。
【犬ジステンパーウイルス感染症】
発熱やくしゃみ、痙攣、咳などの症状が現われ、場合によっては命に関わる感染症です。
【寄生虫感染・フィラリア症】
ノミやマダニなどの外部寄生虫や、回虫やフィラリアなど内臓に寄生する虫がいます。寄生虫は貧血でぐったりしたり、蚊から媒介して感染するフィラリア症は心臓などに寄生されると重篤な症状を引き起こします。
熱中症

暑さで体温調節がうまくいかず、
・高温のアスファルトの上を長く散歩していた
・エアコンが効いていない室内で長時間留守番していた
・炎天下の車内で放置されてしまう
などの後にぐったりしていれば、熱中症の可能性があります。
熱中症の主な症状は、ハアハアと苦しそうな呼吸(パンティング行動)、嘔吐、脱水、意識障害などです。
熱中症は夏に多く見られる傾向ですが、冬にも暖房が効きすぎた室内などで起こることがあります。
低血糖
血糖値が異常に低くなる「低血糖」は、脳と筋肉に影響をおよぼします。
子犬や小型犬で起こりやすい症状で、
・意識がもうろうとしている
・動きが鈍い
・力が入らずにふらすいて歩く
・急に倒れて動けない
などが見られます。
脳の主な栄養源である“ブドウ糖”がなくなると神経系に影響するため、反応も鈍くぼんやりし意識朦朧となったり、エネルギー不足の筋肉に力が入らずに「立てない」「ふらつく」とぐったりすることもあります。空腹のときや激しく運動したときに低血糖が起こりやすいと考えられています。
誤食・誤飲
犬は「口に入れて確認する」という習性が本能的に備わっている動物で、有害なものを口に入れて中毒症状を起こすことがあります。
代表的なものは、
・玉ねぎ、長ねぎ、ニンニク
・キシリトールガム
・チョコレート
・ぶどう、レーズン
・タバコ、アルコール
・洗剤や漂白剤
・人間の薬
・観葉植物
などです。
これらの誤食や誤飲でぐったりすることがあります。
誤食や誤飲は犬の消化器系に影響を及ぼし、
・プラスチック片など鋭利なものが口内や喉に刺さっている
・異物が胃を刺激し嘔吐や腹部の痛みを起こしている
・異物が腸を通過できずに詰まっている
・消化管に穴をあけてしまっている
など、重篤な症状が起こるケースもあります。
短時間で命に関わる症状が起こることも少なくありません。
内臓の疾患
腎臓や心臓、肝臓、膵臓などの「内臓」の異常から、元気がなくなることも考えられます。
食欲不振から体重が減り、震える、呼吸が荒いといった症状が起こるケースもあります。
腎臓病や心臓病など慢性的な疾患の場合、徐々に進行するため、日常的に体調を観察しておくことも重要です。
ワクチン接種が原因
ワクチン注射の副作用で一時的にぐったりすることがあります。特に、注射されるのが嫌いな犬の場合、元気のなさが強めに出るかもしれません。
摂取後は安静にしていることが大事なため、次の日には元気が戻っていることが多いです。
しかし、注意したいのは、
・嘔吐をともなっている
・腫れがひどい
・ぐったりが翌日まで続く
などの場合です。
重篤な副反応のケースもあるため、早めに動物病院に行き、獣医師から診断してもらうことが大事です。
ケガ
落下や事故により痛みが強くて元気がないこともあります。
特に足の細い小型犬は室内で脱臼や骨折をしやすく、動けなくなることも。傷みがひどいと触られるのを嫌がり、震えたりもします。
また、外見では分からないものの、内臓にまでダメージ受けているケースもあるため注意しましょう。
胃拡張や胃捻転
嘔吐したいのに吐けず、ぐったりすることがあります。特に、大型犬によく見られる原因です。お腹の膨れもあります。
命の危険をともなうため、一刻も早い受診が大切です。
貧血
腫瘍や内臓の疾患により貧血となり、ぐったりすることがあります。酸素が全身に行きわたらないため、疲れやすく「動きたがらない」様子が見られるかもしれません。
貧血の原因はさまざまで、内臓疾患による出血、免疫の異常や寄生虫などが考えられます。
老化によるもの
犬は人間よりも年を重ねるのが早く、7歳を過ぎると「シニア」です。飼い主様にとっては可愛らしい子供のような存在ですが、老化現象によって元気がないこともあります。
老化でぐったりしている場合、「最近寝ることが増えた」と毎日なんとなく元気のなさを感じでしょう。
ストレスなどの精神的なもの
引っ越しや新しい家族の誕生、ほかのペットを迎え入れたなどでストレスを感じて元気がないこともあります。赤ちゃんやほかのペットが家族に加わると、これまでと大きく環境が変わってストレスを強く感じやすいです。
動物病院へ連れて行くべき犬のぐったり症状や緊急受診のサイン

次のような緊急度の高い症状が見られたら、すぐにでも受診すべきサインです。
呼んでも無反応、意識があまりない
名前を呼んでも無反応だったり、目は開いているのに焦点が合っていないような様子は、脳の働きがかなり低下しているかもしれません。低血糖やショック症状の可能性もあります。
呼吸が荒い・浅い、苦しそう、
ハアハアという呼吸が荒々しい、胸を膨らまして苦しそうなどは、呼吸器や心臓の異常かもしれません。熱中症の可能性も考えられます。
呼吸困難の異常は、短時間で命に関わる場合も多いため、一刻も早い受診が大切です。
痙攣や震えがある
身体の硬直や痙攣、震えが止まらないときは要注意です。痙攣が何度も起こる場合は、脳に深刻なダメージがある可能性もあり、すぐに動物病院に行きましょう。
下痢・嘔吐を繰り返す
何度も繰り返す下痢や嘔吐は、脱水症状のリスクが高いです。その原因が中毒や急性の内臓疾患の可能性もあるため、症状がひどければ早めの診断が重要です。
尿に血が混じる、尿が出ない
尿に血が混じると膀胱炎や腎不全などの可能性があります。尿が出ないのも、尿路閉塞、膀胱炎などが考えられます。
排尿の異常は命に関わる可能性もある緊急度が高い状態です。すぐにでも動物病院を受診しましょう。
食欲がない、食べない
犬がぐったりしていると、ごはんを食べないことも多いです。食事の量が減っても、少しずつでも食べているなら様子見でもいいことがあります。
しかし、「丸2日も食べない」「水も飲まない」など飲食を長時間受け付けない状態なら早めの動物病院をおすすめします。
高齢の犬の場合、そもそも食事量が若いときよりも減ってくるのが一般的。食事量の減少が免疫低下や病気のサインのこともあり、注意しなければなりません。
1~2時間以上もぐったりしている
意識レベルや痙攣などがないと、まずは様子見をする方もいます。ただし、子犬や高齢犬が1~2時間以上もぐったりが続いているなら、注意が必要です。なるべく早めに受診しましょう。
【まとめ】犬がぐったりした時に飼い主が知っておくべき大切なポイント
「いつもよりも元気がないけれど呼びかけにも反応するし食欲もある」
「名前を呼んでも反応しない」
そんなとき、飼い主様は心配で不安で仕方がないですよね。様子見しようかどうしようか迷うかもしれません。
まずは慌てずに落ち着き、愛犬を安静にしましょう。
以下の症状は緊急度が高いため注意が必要です。
・意識がない、反応が鈍い
・呼吸が速い、苦しそう
・下痢や嘔吐がひどい
・痙攣や震えが続いている
・尿が出ない、血がまじる
熱中症や内臓疾患、感染症などの場合、できるだけ早めの診断・処置が必要なケースも少なくありません。無理に動かすことで余計に状態を悪化させることもあり、意識障害や嘔吐があるときに無理に水を飲ませると誤嚥のリスクが高く危険です。
明らかに異変があるときは、速やかに動物病院を受診しましょう。早期の診断と適切な処置ができるのは、専門知識を持つ動物病院です。独自の判断で様子見をするよりも、愛犬の命を守ることにつながります。
また、夜間に愛犬がぐったりすると「明日まで様子を見よう」と受診を控えるケースもあるかもしれません。でも、その数時間が命を脅かすこともあるのです。
当院は、東京・横浜・川崎・千葉の京浜エリアで深夜のペット診療(夜間動物病院)を行っています。愛犬の異変で受診をご希望の場合には、お電話にてご予約のうえまずはご来院ください。